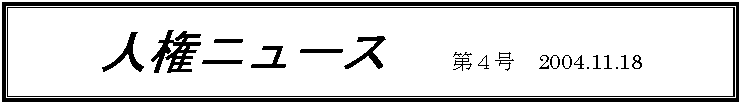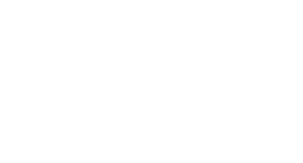広 瀬 徹 1.わたしの出発点 33年前、尼崎工業高校へ非常勤時間講師として赴任した私に、「先生、足どないしたん」と直截に聞いたのが部落研の生徒たちでした。そのような問いは、相手に対してかわいそうだ、失礼だとして直接聞かれたことは少なかったわたしですが、そのときの生徒たちは違っていました。その人の一番大事なところを抜いては本当のつきあいはないとそれまでの活動で分かっている生徒たちでした。 6歳のとき、 このことを抜きにせず生徒とつきあってきたように思います。その生徒の一番大事な根幹のところを直接話しかけて聞き取る。聞いた限りはきちんとつきあう。一緒に動きながら、そのことをいつも大事にしてその生徒とともに生き方を考える。そのように動くことを先輩教師から、生徒達から学びながらこれまでやってきました。 本当に荒れた時代がありました。初めて職員室で面接を受けた時、「君、イスがとぶけどいいか」と言われたのを覚えています。言われて下がるくらいなら来ていません。「ハイ」と言うんですが、1年くらい後でしたか、ほんとうにそんな場面に出会いました。突然、イスを振りあげて生徒がケンカを始めたのです。「そのとき瞬時に割って入るかどうかや、生徒はケンカしとうてケンカしてるのやない。生徒の目を見れたら大丈夫や。」その通りでした。瞬間的に間に入るとほんとうに止まるのです。そんな場面が何回かありましたが、すぐに間に入れば、必ず教師の顔を立てる形でいったん収まるのでした。 何名も単車で命をなくさせました。数珠がはなせない時期もありました。若い生徒のお葬式はたまらないものです。 「広瀬くん、なあ、生徒が誰も分からんところで窓ガラスをたたき割ってる時、生徒の表情、想像できるか、顔、つらそうにゆがんでんのやで」そう話してくれた先輩教師を今でも忘れません。 奨学金とか生活扶助とか勉強とか、やれることをやったとしても肩代わりできないものがあります。しかし人は不思議ですが、その事を分かってくれる人がいる、横にいてくれる人がいるというだけで気持ちが楽になることがあります。教師という仕事はそのような仕事ではないかと思います。 2.出会った生徒たち 自分を見つめ直し成長するたくさんの生徒たちと出会えました。 かつがせてもらえなかった御輿の話しを聞き取り、それなら御輿を作ってそのことを舞台劇にしようと、御輿作りからとりかかった部落問題研究部の生徒たち、御輿作りの名人にお会いし、図面からていねいに教えていただきました。 加藤清正や豊臣秀吉が、朝鮮の人々から見れば突然現れた武力侵略者であること、私の知らない歴史の見方でした。そしてほんの100年ほど前の江戸時代、朝鮮通信使はその瀬戸内の宿泊地ごとに文化人が訪ね来て教えを請うという文化使節使でもあったということ、日朝の負の歴史だけでなく、正の歴史もずいぶん学びました。 受け持った在日朝鮮人生徒に、「先生、朝鮮という文字の意味知ってる? 昨日親父に教えてもらった。朝日の鮮やかな国と書いて朝鮮と読むんやで。日の本よりはっきりしてるやろ。」と話してくれた生徒のことは、今でも生徒たちに伝えることとして、大切にしています。 2年の修学旅行として船旅で奄美大島へ行こうという計画を実現させた同僚教師団は、その生徒達が卒業するときの予餞会を、奄美大島から、交流した老人施設の幾人かの皆さん、教えて頂いた奄美民謡の先生方を招待し、尼崎に住む奄美・沖縄出身の皆さんを保護者のつてを頼りに依頼し、終日アルカイックホールを借り切って「奄美・沖縄の風にふれる」という文化行事として実現させました。 つい最近、その日のビデオを見つけ、DVDへの焼き付けを行ったのですが、今思えば、「地域との連携」「総合的学習」「心豊かな生き方」といったテーマをひとつひとつ実践していたのだと位置づけられます。むしろそれらのテーマが後追いをしたのでしょう。 それまで酒を飲む親父だとしか思っていなかった生徒が、私が借りに行ったとき大量のレコード盤を出してくれてひとつひとつていねいに説明している父親の姿を見て、「親父、酔っぱらってる時、いつもそのレコードかけてるわ。」と初めて気づきます。そのレコードの中から彼は、輪になって踊る唄「ワイド節」を選んで、次の年、部員達と文化祭の舞台で踊りました。お父さんとお母さんが舞台の一番前にいてくれました。 こうした被差別のこどもたちの動きは、クラスの生徒全体を巻き込んでいきました。 旋盤工の親の生き方を聞き取り、授業参観の日、お父さんにその話をしてもらうようにした生徒、籍が違ってしまった父を「あんな親父なんか親父やない」と言い切っていた生徒が、これらの話に触れるうち、「一回、親父の気持ち聞きに行くわ。」と母に了解してもらって、会いに行きました。今彼は、別に暮らす父の元へ孫になるこどもを連れて顔を見せに行っています。 わたしたちは、卒業生に会うと「親孝行してるか、だいじょうぶか」と言ってしまいます。ほとんどの卒業生が即座に「大丈夫や。それだけは守ってる。」と言ってくれます。話しの中で、「守衛さんにあいさつしてるか、掃除してくれてるひとにあいさつしてるか。」と聞きます。職場の中で下積みとして働いておられる人が一番その職場の事を分かっておられる、そこへきちんとあいさつできないと「働きびと」と言わへん、と9割が就職していた当時、進路指導担当の先輩教師から教えてもらったことでした。 わたしたちの生徒は、それを守ってくれているようです。何百人と卒業生を働く人として送り出しました。この阪神の地に、そのことを大事にしてくれる人たちが、もう30代、40代の親としていてくれる。わたしは阪神の同和教育が生みだした大事な財産だと思います。 3.普通校でも同じ事が起こっている 13年半尼崎工業高校に勤めまして、普通高校西宮南高校へ転勤しました。 普通校でも生徒は同じ事でした。当時、私は「生徒は、砂漠の中で乾いている。」と思いました。武庫川団地の高層団地群に住む生徒の幾人もが、帰っても誰もいない、電気の点いていない部屋へ入ることを知りました。 そのことをきちんとつかみ、生徒達の乾きをいやして、元気づけ、希望する進路を実現させようと苦闘されている先生に幾人も出会いました。在任中2回組んだ担任団の方々とはいろいろな思い出があります。2年次、進級できないとわかった女生徒の家を訪れ、お父さんに「お母さんの代わりをしてきたこの子を高校卒業させないで辞めさせたらいけません」と必死に説得しているとき、「わかった、先生、お父さんをせめんといて。私、留年して学校へ行くから。」と言うところまで動いた同僚がいました。その生徒は以後2年間、ほとんど単位を落とすことなく1年遅れで卒業しました。私たちはその子にお祝いの花束を贈ったものでした。 「先生、今度文化祭で沖縄のエイサーを踊ることになりました。足りない衣装や太鼓を借りれないでしょうか。」と同僚教師が言ってくれました。すぐに同僚であった尼崎工業高校の沖縄問題研究部顧問に連絡を取ります。「いいですよ、どうぞ。普通高校で出来ますか、うれしいですね。」という言葉をもらって生徒達が、借り受けに行きました。阪神で活動する「琉球國祭り太鼓」の青年のみなさんに、リズムのよい、ちょうど北海道の「よさこいソーラン」の踊りのようなアレンジを教えていただき、生徒達はみるみるその魅力にとりつかれました。文化祭当日、力一杯踊りきった生徒達は遅れて見に来れなかった保護者がいることを聞くと、「もう一回みんなで踊りたい、運動場で踊っていいか。」と、保護者に囲まれながら、もう一度踊った事を後で聞きました。 こうした同僚教師の、生徒と寄り添いながら激励し鍛えるという動きにいくつも出会いました。 人権ロングホームルームをいつも、自分の視点で作り上げ、できるだけ生徒に話させるように動いていた同僚教師の3年次のホームルームで、一人の部落出身の生徒が自らを名乗っていく場面がありました。「わたしは部落出身です。今の世の中で差別は実際にありますから、就職や結婚で出会うかも知れません。そのことを考えて私は看護士になりたいと進路を決めています。」とクラスで、話したのだと聞きました。すぐに話しに行きます。「わたしはっきりさせときたかった。」ときっぱり言い切りました。 その直後でした。高校の同窓会があり、関西に赴任してきた親友に何十年ぶりかで会えたうれしさで酒を過ごした私は、深夜転倒し頭部を強打する大けがを負いました。義足は膝がしらを固定しますから、倒れる時、かかとを支点としてまわるように倒れ、頭部を強打したのでした。 病院のベッドで考えたことの一つは、ありのまま出直そう、ということでした。彼女が級友の前で部落出身を明らかにした行動は、私になにか促していました。片足であることを隠す義足を止めることから再出発しようと思い決めました。二十歳の時以来、人目には足を引きずっているとしか見えない自分を、本来の自分にもどそうと思いました。実は、重い義足を肩からバンドでつり下げているのは大きな負担です。家では私は義足をはずし楽にしていました。倒れた時の危険も大きいものでした。30年ほどの間に、生徒たちから学びました確信がありましたし、障害者運動にも強くたずさわってきました。障害者であることに迷いがないところまできていたように思います。ありのままが一番いい、ずっと生徒達が言ってきた事を自分もやっていくことにしました。 4月1日から義足をはずし、松葉杖姿で勤務を始めました。最初の職員会議、最初の授業でこの気持ちを同僚と生徒たちに話しました。生徒達は面食らっていました。「先生、どないしたん。」何回も聞かれました。聞いてくれるのは大事です。そのたび、「うん、ありのままが一番いいから」とていねいに気持ちを話しました。不思議ですが、1ヶ月もたつと、何でもない日常のことになります。今でも思わず笑ってしまうのですが、人権講演会で車いす障害者の講師に話しをしてもらった後の感想文に「わたしは日頃余り障害者に接したことがないので・・・」という生徒の感想文にいくつも出会います。毎日、黒板を前に私を見ていますのに・・。実は「障害者」とか「被差別」ということがらは本来このような正体のないものなのでしょう。それを、人の心が形あるものとし、実態を持つ差別へと変じさせていくのだと思います。 4.学校改革の中へ、進路保障と学力保障 13年勤務した西宮南高から、転勤願いを出し尼へ戻れることとなりました。 新しい赴任先、県立尼崎高校の着任の会合の時、「県尼改革」と題する3冊の冊子を渡されました。そこには様々な現状分析と共に、ここ10年ほどの退学者数、生徒指導件数など赤裸々な数字があがっていました。本気でこの現状に取り組もうとされていると思いました。その数字の中から生徒の悲鳴が聞こえると思いました。 授業中に塀を乗り越え「中抜け」する男女生徒が後を絶ちませんでしたし、トイレのタバコは常時見回りを必要としていました。乱暴な言葉使いが氾濫していました。「先生、あの子らはx、yが分かりませんからレポートで評価して進級させて下さい。」と教科主任から最初話しがありました。 しかしすぐにいろんな生徒に出会います。「先生、足どうしたん。」と聞いた生徒は何人もいましたし、自分のやけどの痕を見せてくれた生徒もいました。文化祭では、見事な踊りが朝鮮文化研究部で伝統的に続けられ、花束を涙と共に贈る恒例の引き継ぎもおこなわれていました。「県尼では咲いている花が折られたことはないんですよ。」と話して下さる先生がいました。家庭の事情を抱えながら3年間手を抜かなかった生徒は、私の授業中、どれを聞いてもかなりのところまで答えられる力を持っていました。 この生徒達へ用意されていったのが「県尼改革」でした。窮屈な学生服をスーツに替えることから始まり、10分間の「朝の読書」時間を設け、静かな雰囲気から1日を始めようと動き出していました。 自主的にカリキュラムの改革に取り組みました。1年次は基礎基本を徹底させたいと英数国三教科の少数クラスの実現。従来とってきた、4年制理系進学、4年制文系進学、就職に振り分けたコースを改めて、「学びたいものを学ぶ」という基本にたち、2年次より国語・地歴・公民を中心に学ぶ「人文社会類型」、数学・理料を中心に学ぶ「自然科学類型」、英語・地歴・公民を中心に学ぶ「国際文化類型」、情報・商業を中心に学ぶ「情報科学類型」に分かれ、2年次は5時間、3年時は14時間の類型選択を取り入れました。発足当時7クラスのうち、人文2.5クラス、自然1.5クラス、国際1クラス、情報2クラスから始まりました。 また自由選択教科の中に、学校設置科目「尼崎学」「ボランティア実践」、国際理解のための「朝鮮語」「中国語」の開講を始めました。 様々な新しい動きがありました。「尼崎学」では、連続2時間の授業で、自転車を連ねて田能遺跡や、港までの廃線跡をたどったり、活発な授業が続けられています。「ボランティア実践」の授業から近隣のお年寄り施設との交流、講演会での生徒による手話通訳などが実現しています。 3年前から先んじて始められた「総合的学習の時間」では1年間の討議と準備を経て、「Self−Navi 〜輝く自分を見つけるために〜」と題する週1時間の授業を始めました。「自分の夢を語る」から始めて、生徒自身の電話依頼から始まる体験学習、仕事調べ、講師をそれぞれおよびする「班別講演会」、最後に「全体スピーチ大会」を開き、自己表現を磨きます。 この「Self−Navi」の授業は、これまでに生徒たちの気持ちに寄り添いながら共に泣き笑いして続けてきた同僚教師の教科や課外活動の延長にあります。自己を精一杯表現する喜びを引き出して来た動きがあっての事でした。 4年前に体育女子創作ダンスの授業内の発表をきっかけとして、放課後体育館のステージで思い切り動く「ダンス大会」として組み立てられた自主行事は、今では定例となり、文化祭での舞台部門の主要な出し物の一つとなりました。 30人が舞台狭しと乱舞する「よさこいソーラン」の踊りは、韓国修学旅行を実施した学年団が「県尼に新しい風を吹かそう」と生徒たちと心を合わせて始めたものでした。これはその秋、韓国修学旅行で釜山南高校との交流会の舞台で力一杯演じられました。 類型選択の授業で行われるディべードの授業は社会や国語の教師によって日常行われています。また類型選択「国語表現」でも、生徒の一人一人の感性を大切にした授業が行われており、一人一人の最後の文章発表では、それぞれの一番大事な表に出したこともないことがらが次々と書かれ読まれていく場面に授業参加できたこともあります。20数年前立ち会った生徒たちのホームルームと重なるものでした。 カリキュラムを変えて7年になります。ずいぶん学校がかわりました。 授業中塀を乗り越える姿、タバコのにおいのするトイレ、騒然とした全校集会がなくなりました。ここ3年ほど、どの学年、クラスも真剣に唄い、ピーンと張りつめた空気の中で行われる文化祭合唱コンクールが続いています。「もう合唱コンクールなんかやめようか、生徒たちには無理や。」と言いかかっていた私達でしたが、そのときから言えば「奇跡」と思えるこの生徒たちの集中ぶりは、あり得る未来を指し示し、私達へ勇気を与えてくれる大きな力です。 そうです、生徒会の作った昨年の体育祭のスローガンは「ガンバルきみが一番だ!」というものでした。100メートルを始めどの競技もクラスで応援し、一生懸命走る生徒の姿が当たり前となっています。 到達できていない学力保障、進路保障があります。 7年前に続いていた、入学から卒業までの3年間に留級・退学・転学者が30名〜40名にのぼる数字が改善できないまま続いています。カリキュラム改革最初の卒業時、30名を切ったこともありますが、依然として1クラスに及ぶ生徒を抜け落ちさせています。 私は当初、学校が落ち着けば、留級者・退学者は減ると予測し、まずその落ち着きを目指しました。授業としてずいぶん静かになりました。しかしうつぶせになって授業に参加していない生徒たち、じっと聞いているけれど試験では0点に近い理解度である生徒たちへの手だてがまだ確立していません。内容を理解させていないのにレポートなどで単位認定をするごまかしは止めたい。そういう生徒ほど分かりたがっている、分かった時大きな元気を出す、という舞台や合唱コンクールでつかんだ予感はあるのですが、まだ実践として作りだし、拾い出せるところへ来ていません。 点数不足で不認定となる生徒、なくしてしまった登校意欲を取り戻させることができずに出席不足で不認定となっていく生徒が、1クラス分いるのです。その中に間違いなく被差別にある生徒たち、家庭的困難を抱える生徒達が高率に混じっています。 本校の通学区域は 大人の状況はまちがいなく子供たちの状況へ押し寄せますし、アルバイトで小遣いを作るのはもちろん、学費を捻出している生徒も珍しくありません。 これらの生徒へ、進路を切り開く学力へ向かう意欲をつけるとすれば、勉強のおもしろさをまず伝え、切り開けるとする進路の実際を教師側が明らかにしなければなりません。 今年も真剣に国公立大学を目指している生徒が何人もいます。いっそうの経済的困難さの中で、国公立でない限り進学できないという生徒たちが増えています。公立学校としての責務はこの生徒たちに進路を実現させることを含むと思います。AO入試、自己推薦入試も含めて、自己表現力をも研ぎすまして進路に立ち向かわせたいと多くの同僚教師と心を合わせて動いています。 5.自分の持ち場の中で、生徒に寄り添うことから始めませんか 同和教育が人権教育と名前を変え、同和対策特別措置法2002年終了を受け、教育現場に若干の迷いが感じられます。しかし今ほど、長い同和教育の実践の中で培ってきたことが必要とされている時代はないのではないでしょうか。「人の痛みを知る」「心豊かな生き方を探る」「多様な生き方から学ぶ」「地域と連携する」・・・これらのテーマは私達の先輩教師が、生徒や親と歩む中で探し当てたテーマであります。 もういちど原点に帰ればいいだけではないでしょうか。自分の持ち場の中で、生徒たちに寄り添うことではないでしょうか。 私の持ち場は、数学教科担当、情報教科担当、図書部長と人権教育推進委員会委員長です。 数学の授業の中でひとりでも不認定を出さない、試験で30点以上点を取らせて認定する、数学にそっぽを向いている生徒を1回でもいいからこちらを向かす授業展開・教材・教具を工夫する、若い先生方につかんできた授業論を伝える、まずこれが仕事です。 情報科目では「自分を表現する」道具がコンピュータであることをとことん伝えます。ワープロを教えるなら、「おとうさん、おかあさんのための旅行計画書」の作成を提案します。家庭状況をつかんだ上で実施します。「おかあさんだけのおうちは2倍苦労をかけてるから、2倍いいプランを作ろう」と呼びかけます。ホームページ作成を教えるなら、一人一人違ったテーマで、「一番自分を輝かせるものでホームページを作ろう」と呼びかけます。情報教育推進委員会に図った上で、無料ホームページ保存場所を取得させ、本物のホームページとして卒業後も維持できるものとします。デジタルビデオで生徒の活動を記録している若い先生方へ、生徒たちへ配って喜ぶ顔を見てもらうため、CD-ROMに編集・記録できるよう技術講習会を開いています。 図書部長として、図書館へ避難してくる生徒とていねいにつきあいます。図書委員になってくれた彼らは、膨大な本の整理や、明るい図書館への配置換えにボランティアとして力を貸してくれます。ホコリのかぶった、もう生徒が借りてくれない本を書庫へしまい込み、まず生徒が読んでくれそうな本を図書予算を整理して購入しています。今年は読んでほしい本へと幅を広げています。人権コーナー、国際コーナー、進路コーナーを特設するのも今年の目標です。まだ静かとは言えない「10分間朝の読書」をほとんどの生徒がシーンとして本を読んでいる「奇跡」を実現できるはずと自らを鼓舞して、資料を出し続けています。 人権教育推進委員長として2年目、特に気づくことがあります。 確かに、直接の部落問題、朝鮮問題が表舞台に出ることは少なくなっています。もちろん現状の中で出しあぐねている私自身の問題でもあります。しかし、人権そのものに係わることがらや報告や取組はとても多くなっているのです。 2年前から学校として修学旅行先を韓国と決定して動いてきました。その前後、たくさんの時間が一番近くて遠い国とされていた韓国・朝鮮の理解へ費やされます。200人を越える若者が実際に韓国の人と風土に触れてくるのです。 総合的学習の時間では、人権や人間に係わるテーマや講演や体験学習が生徒の自発性の中で実行されます。 自由選択で朝鮮語を習った生徒の中から、韓国へ留学にでる生徒が出ています。 校内研修会で、そのことを伝えるためにまとめていて、改めてその広がり、多様性に気づきます。 研修会で、難聴生徒と寄り添う3年間の取組みを話してくれた同僚教師は、最後に「私の気持ちを全部伝えたい」と級友へ読んだ手紙を紹介してくれました。 わたしも先ほどから紹介した多様な取組の中で見せてくれる生徒の輝きに出会う時、幾人かの生徒と深く話すことが出来るようになりました。 入学時、県尼が伝統として続けている貴重な入学式当日の取組み「外国籍生徒・保護者の集い」では、朝文研の先輩や韓国籍の同胞教師に囲まれた元気のいい女生徒Aさんと出会えました。そのときに強く勧めました朝鮮奨学会へ、応募するという申し出がありました。担任と一緒に書類をそろえます。その時点で中学時の評定平均が奨学会の応募資格とする3.0を越えていないことがわかりました。しかしその欠席日数が私達に伝えるものがありました。1年、2年の10日を超す欠席日数に対し、中学3年時の欠席日数は0日でした。担任が話しを聞き取ってくれます。朝鮮人である父と母が離婚したこと、鹿児島まで家出をしていたこと、中3の時再婚となり日本人の父が出来たこと、自分の学資を出してくれている父に遠慮して、学校へちゃんと行きだしたこと、ちょっとでも負担を減らしたいので奨学金を受けたいことを話してくれました。朝鮮奨学会関西支部へ申請書を届け口頭でお願いしたのですが、面接にさえ進めそうにありませんでした。帰校して急遽担任と相談し、副申書を書き上げもう一度奨学会へお願いに行きました。関西支部長が会っていただき、東京で開かれる審査会でも理事に見せると言っていただきました。次の日、そのことをAさんに伝えました。残念ながら結果は不採用でしたが、以後担任とともに、たくさんの話しをする間柄になりました。 それでも授業の中では、ハリネズミのような反応が強く、授業の先生方とよく争いごとが起こりました。面白くない、と遅刻したり、時には母親と連絡を取る担任とすれ違うこともおこりました。私の役目はAさんに声をかけ続けることです。図書館までの廊下を、Aさんに会えるよう通っていきます。何回かにいっぺんはうまく出会えます。精一杯立ち話をして、担任とつなぐことをまず第一のこととしていました。 県尼で続いている恒例の学校行事「外国籍生徒との秋の遠足」(人権教育推進委員会主催)の教師2人、生徒4人の中にAさんが来ました。「バイトがあるから」と答えを渋っていたのですが、遠足の朝、電話すると、お母さんが「今、行ってくると出て行きましたよ。」、うれしい1日でした。太秦広隆寺の弥勒菩薩を見に出かけ、太秦の土地が渡来人秦氏の住む土地だったこと、大きな文化財産を朝鮮半島から受け取っていることなどを、参加した朝鮮人生徒とともに話が出来ました。 3学期の学年末考査時、教科勉強を図書館でやったこともありましたが、それまでの意欲不振がもとで留級となってしまいました。まだハリネズミ的な様相は取れていないのですが、留級生のほとんどが退学又は単位制高校へ転学している現状をAさんならくぐり抜けられないか、声をかける日が続いています。 10月14日、今年の人権教育行事として「新井英一、清河への道を唄う」と題する音楽公演会を実施することが、7月の職員会議で正式に決まりました。 「アジアの大地が見たくって俺はひとり旅に出た」と歌い出す48番のギターの弾き語りは、お父さんの故郷、慶尚北道清河を訪れたことを出だしに、九州での生い立ち、神戸へ出てきたこと、アメリカでのブルースとの出会い、東京生活、愛する家族、自らのルーツを語るものです。当初、公演を打診した時、電話に出られた新井さんは「生徒さん、45分間持ちますでしょうか。」と言われました。9年前、アルバム部門レコード大賞を受けた時、すぐにCDを買って深夜ヘッドホーンで聴きながら、茫としてあふれる涙を抑えることが出来なかったことを西宮南高の学校新聞で卒業する生徒達へ書いたいきさつは話していましたので、その気持ちを込めて「大丈夫です。県尼の生徒は聴き取れます。」と返事しました。「分かりました、私も48番全部を唄うのは年に2、3回しかないのですが、そういうことであれば、やりましょう。」と力強く言っていただきました。 わたしは歌一つで人間は死ぬことをやめることがある、生き方を変えることがあると信じている一人です。Aさん始めたくさんの県尼生に、新井さんの野太い声の「清河への道〜48番」を聞かせたい、とてもそう思います。9月から、新井さんを迎えるための全校集会での呼びかけや、「人権ニュース」の発行や、一人一人生徒へ伝えていくことを始めています。ドキドキしますが、きっと県尼生は深いところで新井さんの唄を受け止めてくれると思います。 今日、お集まりの皆さんにもいっしょに、身近にいる思い悩む生徒、揺れ動く生徒に寄り添うことから始めることをよびかけます。日常の何気ない会話、何かあった時まっすぐ声をかける、担任につなぐ役目をする、そのことで生徒が学校の中につながり、進路を切り開くきっかけとなることを願って動いていきませんか。 2004年9月29日 【追記1】
新井さんの歌声とお二人のギターが体育館に響きました 10/14(木)1時半より、「人権教育行事:新井英一、清河への道を唄う」が開かれ、たくさんの生徒の皆さんの反響がありました。 1.新井さんの事で伝わっていなかったことがいくつかありました みなさんの作文を全部読ませてもらいました。いくつか、私たちが事前に十分伝え切れていなかった事がありました。 「朝鮮人と間違われた」>新井さんのご両親は朝鮮半島から日本へ来日した朝鮮人です。新井さんも現在は日本へ帰化していますが、自分のルーツは朝鮮人であることをはっきりさせています。 「歌手になる夢を実現させて下さい」>新井さんは8年前、アルバム部門レコード大賞を受けたブルースシンガーです。全国で演奏会を開くプロのミュージシャンです。 唄った歌詞の中で「電線ドロボーの品物をおふくろが買っちまったために贓物故買(ぞうぶつこばい)と言う罪で地元の新聞に載せられて母は刑務所に送られた」の意味が分からなかったという人が多かったのですが、「盗品などによって手に入れた財物をそれと知っていて買ったとみなされた」という終戦後の混乱の中でよく起こっていたことでした。 2.新井さんへの感想文で、多かった大事なことがらをあげてみます 「48番を聞くのはしんどかったけど新井さんはもっとしんどいと思ってちゃんと聞いた。」 >県尼生はこう気付いてくれる人が多い。とても大事なことだと思います。 「命を削って唄う、と言っていたのは本当だと思う。」「最後まで太い声で唄った。やはりプロはすごい。」「40分間弾き続けていた横のギター伴奏者の高橋さんがすごかった。」
ったのです。 「新井英一、清河への道を唄う」が実現できてほんとうに良 かったです。 「お母さんを迎えに塀によじ登ったというのが一番心に残った。」 「お父さんの死に涙が出なかったのはふしぎだった。」 「本当に家出して一人で生きていくなんてわたしには出来ない。」 >多くの人が、自分の家族と重ね合わせて聞いてくれていました。 3.人権問題を考え直したり、自分の生き方を考えていこうと何人もしていました とても大事なことなのですが、「新井さんは必死で伝えようとしていた」と何人も書いていました。 「朝鮮人と言われていじめられたのはつらかったと思います。」 「実際、在日の人々の苦労を歌う人達が、新井さんを始め沢山の人らが叫び続けても、変わらない現実が不思議だ。」 2年生は韓国修学旅行へ行って来たばかりです。きっと新井さんの事も思い出していたと思います。感想を聞かせて下さい。 新井さんの歌を聴いて、改めて自分の生き方を考えた人も多かったです。 「新井さんが最後に“青春を楽しめよ”と言ってた言葉はすごく心に残りました。学校は楽しいことばっかりじゃないし、つかれる事もいっぱいあるけど、今の間にいっぱい笑って、楽しく過ごしていったら、最後には大きな思い出になって心にのこるんだろうと思えました。」 「私も新井さんのようにおもいきった人生を生きてみようかなぁ・・・と思いました。」 「ミュージシャンの夢を捨てることなく、自分の道を歩いていこうと思います。」 そして県尼の中の韓国・朝鮮人の生徒の皆さんも、大きな励ましをもらったようです。 「僕も自信を持って、また朝鮮人としての誇りをもってがんばって行きたいと思います!」 4.新井さんの歌をもっと聞きたい、という声が多かったです 新井さんの公式ホームページはhttp://www.e-arai.com/ です。 発売されたアルバムのそれぞれの歌の1小節だけなら直接聞くことが出来ます。
ライブスケジュール: 12月26日(日)、大阪梅田東側の「バナナホール」 ※ 今、皆さんの中から3つほどクラス全員の感想文を届けています。返事が来たらまた載せます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
魂の歌をありがとうございました 1年 A 新井さんの魂が伝わってきた気がします。僕も新井さんと同じ立場の人間なので、グッと来ました。そして何よりも元気が出た気がします。ぜひ、もう一度“清河”を聞かせてください。僕のお母さんとお父さんも、一度、新井さんの歌を聞いたことがあると言ってました。今度はぜひ家族で聞きに行きたいと思います。もし、いつか僕が何かにつまづいたとき、この歌が必ず役に立つと信じています。だから、在日朝鮮人の方にはぜひおすすめしたいと思います。そうすれば、もっと強く生きていけると思います。僕も自信を持って、また、朝鮮人としての誇りをもってがんばって行きたいと思います!
今日は、魂の歌をありがとうございました。 弾く方はもっと疲れたと思います 1年 B 15歳で家出をした事にはびっくりさせられました。それからアメリカに行ったりと、新井さんはいろいろな道を歩んできた事がわかった。国籍とか民族にこだわらず、自由に生きていきたいという気持ちは同感した。『お父さんがなくなった。涙がでなかった。』でも、お父さんの生きてきた道のりを辿って清河に行った事はすごくいい事だと思った。やっぱり自分の国の事は知っておくべきだと思うし、それにお父さんのふるさとを知れるし・・・。 自分にもこれから、どれだけ長い道のりが続いていくのか。苦しいこともあると思うが、自分に素直に生きていきたいと思った。 約50分間、聞く方も疲れたが、弾く方はもっと疲れたと思います。実際に起こった事とかを率直に歌にしていてわかりやすかったです。受け取り方はみんな違うと思うけど、新井さんの思いは少しだけ伝わったと思います。 新井さんと握手しました 1年 C 10月14日。きょうは1時間目から英語の授業と代わって、5・6時間目に来る新井さんの歌のセットを体育館でやった。その時、あんまり見たこともない人もまじめに手伝っていて「誰やろう?」とか思ったけど、あんまり深くは考えずにいたら、用意をしているとき、広瀬先生に呼ばれて「えっと、この人が今日うたってくれる新井英一さんで。」と言われてびっくりした。さっきまで手伝ってた事務の人と思ってたおじさんがそうやったから。 そんで、初めてしゃべった印象は、やさしそうで、強そうな大人の人やなと思った。そして、何時間か過ぎて、5・6時間目になって、少し話も混ぜて歌を聴かせてもらって確信した。この人は本間に心の広い強くてきっと理想の大人の人のような気がした。 話は戻るけど、1時間目、何でか先生に呼ばれて行って、新井さんとはなしたとき、新井さんの方から、私に握手してきてくれた。その手は力強く握られたけど、やさしかった。大人は私たちよりはるかに長く生きているから、大人の人のいい人か、悪い人かなんて、大抵わかる。 ものすごく集中して聞いた 1年 D 新井英一さんの「清河への道」を聞いてとても良かったと思います。新井英一さんの自分の生き方についての歌だった。48番までの長い歌だった。最初は48番とか長すぎて絶対にだれると思っていたけど、聞いてみたら、新井英一さんの生き方がわかってきた。だからその歌の生き方の絵が、頭の中に思い浮かんでいった。歌をものすごい集中して聞いてみると、ものすごい新井英一さんの想いが伝わってきた。 歌の話は、母親が刑務所に入って、それから中学校でいじめられて、そっから家出をして、中学を卒業していないって言っていた。でも家出中にも自分の夢を持っていて、くじけずにすごいと思った。 ただ単に在日とゆうだけで、今はなくなってきたけど、差別されたり、いじめられたりしていた。 僕も新井英一さんみたいに、自分の生き方に誇りをもっていたいと思います。今日、新井英一さんの歌を聞けて本当に良かったと思っています。新井英一さんの歌を聞けて、本当に良かったと思っています。新井英一さんの歌を決して忘れずに生きていきたいです。 新井英一さん、今日はありがとうございました。 私も将来、お爺さんの故郷を訪ねてみます 3年 E 私は在日韓国人です。私は一回も韓国へ行ったことがないので、羨ましかったです。私も将来、お爺さんの故郷を訪ねてみたいと思っています。 48番の唄は、新井さんのすべてがつまった歌だと思います。良い歌でした。ありがとうございます。 あきらめず、やりたいことを仕事にしたい 3年 F 新井英一さんのライブを聞いてとても感動しました。「清河への道」すごく良かったです。48番長かったけど、内容は新井英一さんの思いが伝わって来ました。やっぱりあきらめず、やりたいことをすることは、カッコイイと思います。俺も自分のやりたいことを仕事にしたい。 【追記2】 <ライブにいってきました> 12/26、大阪のバナナホールというライブハウスへ新井さんに会いに行ってきました。 中年、老年の混じった年末の熱気のあるライブでした。10月に出したばかりのアルバム「生きる」からの曲が中心でしたが、体育館のリハーサルのとき歌っておられた曲が何曲かありました。 日本のブルースです、として「炭坑節」が歌われました。「月が出た出たー、月がー出たーよいよい」と新井さんの野太い声が聞こえたとき、ふるさと上山田駅の駅員さんたちが家で宴会を開くときいつも聞こえていたことがよみがえってきました。上山田炭鉱の石炭を送配する鉄道駅でしたから身近な唄で、父たちが酔ったときに必ず歌う唄でした。 わたしもそうでしたのに、いつしか歌わなくなっていた唄でした。 いつかアルバムに出るだろうと待っています。 舞台から降りるとき、来校していただいたことのお礼をもうしあげました。 生徒たちの感想文を、1年、2年、3年の1クラスずつの全員のものを送りました。担任の了解をとり、プライバシーの配慮をお願いして、新井さんには生徒たちの名前はそのままで送りました。 折り返し手紙が来て、「わたしへの手紙と思って大切に読みます。」とありました。 わたしには夢が出来ました。 1970〜1980年代、阪神の同和教育運動の中で育った何百人もの高校生が、今30代、40代になっています。親孝行をする、下積みの働き人のことを落とさない、庶民として生きる・・・、さまざまな言葉で語られたその生き方を、日々の生活の中で底流に置きながら父となり母となっているだろうと思います。わたしの周りにも愚直に生きている卒業生が幾人もいます。 彼らに、新井さんの唄を聞かせたい、とてもそう思います。 アルカイックホールの舞台で、口コミで集まった阪神の卒業生たちが、家族で新井さんの唄を聴くことが出来ないか、あと10年後の夢として描いています。 自分の生き方をさらけ出すことで生きることを見つけ出す、そのことはやはりほんとうでした。 今日聞いていただいた先生方、現場の子供たちのこと、よろしくお願いします。 2005.10.13 |