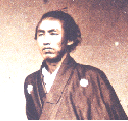
「竜馬がゆくを読みました」
2学年だより(2001年1月9日発行より)
私は、この正月休み、司馬遼太郎「竜馬がゆく」全8巻(文春文庫)を読みました。
鈍才と言われた坂本龍馬が、幕末の攘夷志士とは違った生き方をつらぬいていくその激しさに、もう一度胸打たれました。
薩摩長州同盟をかろうじて成功させ、徳川慶喜に政権返上(大政奉還)させるすれすれの策を実現させた直後、京都近江屋の2階で暗殺されるのです。33歳の若さです。
幕府倒壊を確実にし、無血新政府樹立の希望をやりとげたあと、死に絶えたほとんどの盟友たちと同じ死を迎えていきます。
大きく国を変えていったのは、累々と続く青年たちでした。
おそらく21世紀は未曾有の困難な時代にはいると思います。
そのとき、いやがおうでも時代を背負うのは君たちです。次代をになう青年・・・ という言い方、本当なのです。
借金まみれの国の経済をどう立て直すか。
一気に学力が低下している青少年の教育を新しい流れの中でどうするのか。
わがままが当たり前のこどもたちに親としてどう向かいあうのか。
外国人労働者を排斥しようとする住民をとめられる国際感覚を持てるのか。
でも、きっときみたちはやってくれると思います。
なぜなら、坂本龍馬の生きた時代、今より易しい時代だとは思えないからです。
その時代を竜馬たちは切り抜けて、次の時代を開いてきたのですから。
君たち次代をになう青年ができないとは思えないのです。
その時代、長州藩家老周布政之介などの老壮年はどう生きたか、少し調べてみようと思っています。
龍馬のふるさと、高知を訪ねて
2000.11
第26回全日本教育工学研究協議会全国大会が、200年10月27日〜28日に高知県で開かれました。1年前から取り組んできた情報教育について教育工学の仲間にいろいろな示唆をもらっていまして、その実践報告を持っての参加でした。「普通科高校における1年次からの情報教育−むずかしいけれどがんばる−」としたレポートです。全国いたるところで苦労している仲間との貴重な出会いでした。
次の日が日曜日でしたので、高知へ泊まり、朝から、高知城、そして高知県立坂本龍馬記念館へでかけました。
太平洋をのぞむ高台に建てられた記念館は、一望のもとにひろびろとした海原が見えるような建て方がしてありました。
それまでに読んできた文献の中の龍馬から姉乙女への手紙の原文などが展示されていて、興味深い展示物がいっぱいでした。
そのなかでわたしに一番衝撃だったのは、1枚の掛け軸でした。
それには、墨で「abcd・・」と筆記体のアルファベット文字が縦にかかれてあり、「えー、びー・・」とかなが打ってあるのです。
龍馬たちが土佐青年時代に、オランダ語ではなく、次代を席巻するであろう英国・米国の言葉を学ぼうとした「アルファベット練習ノート帳」でした。
ああ、こうして龍馬たちは勉強していたんだ、と私の生徒たちの顔とだぶってみえました。
凶刃の舞う時代の中で、次代を切り開く青年はこうしたことを積み重ねていたのです。
このことはぜひとも教え子であるみなさんに伝えたいことでした。
残念ながら撮影禁止でしたし、「高知県立坂本龍馬記念館」のホームページにも載っていません。
ぜひ、太平洋に向かって立つ龍馬の巨大な銅像とともに、記念館へ行って「アルファベット練習ノート帳」の実物を見てきてください。
高知県立坂本龍馬記念館のホームページを紹介しておきます。
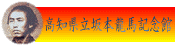
|