「兵庫教育」1995年3月号所収
3次元図形を生徒と共にあやつりたい
−Mathematica を使った数学の授業−
広 瀬 徹
1.はじめに
生徒が数学に目を向けることならなんでもやろう、と始めたコンピュータを使った数学の授業も10余年になります。
受験から離れさせるコンピュータ教室での授業は、非日常の世界へ生徒たちを連れていけます。伝えるべきものを持つことで、授業展開をかなり有効なものにしてくれました。
本年度8月に、40台のWindowsマシン(PS/V Vision)が本校へ導入されました。
2学期来、マルチメディアパソコンとして、情報処理I「自分を表現する」、3年選択英語「Quick English日常英会話」、家庭科衣生活「カラーデザイン帳」の授業が試行されています。
ここ2,3年数学部会でもたびたび話題となっている、高機能数学支援ソフトMathematica を40台分購入できました。
2学期末の2時間ほどの授業を紹介しながら、代数幾何「空間図形」分野の授業をどう組み立てるかを考えてみます。
2.1時間目 Windows入門
2年生代数幾何選択の4クラスで実施しました。
起動しますと、画面はまっ黄色なバラの画像です。「ウワー」と言う声を楽しみながら、まず「マウス体操」です。研修所の上谷氏による命名なのですが、Visual Basicで自作した、Windows初心者用マウス練習プログラムです。
第1体操は「もぐらたたき」でクリックの練習、第2体操は「めだかすくい」でダブルクリックの練習、第3はドラッグ&ドロップの練習で「こそだて」と題してあります。ランダムに出現する虫をマウスでつかまえて待っているひな鳥の口に運ぶのです。
「君ら、もう忘れているだろうけどこんなにして育ててもらったんですよ」と話すとしんみりと聞いています。
あと、ビデオ教材を埋め込んだ日常英会話を紹介して、「マルチメディアにふれる」とするWindows入門の授業を終わります。
3.2時間目 Mathematica を使う
さあ、いよいよMathematicaを生徒たちが使います。たぶん高校で、1クラス40人が1人1台のMathematicaを使うのは全国でも初めての試みでしょう。
ソフトそのものはアメリカ製ですべて英語表示です。はたして生徒たちがコンピュータに無事命令を届けられるかどうか、いささか不安ながら授業を進めます。
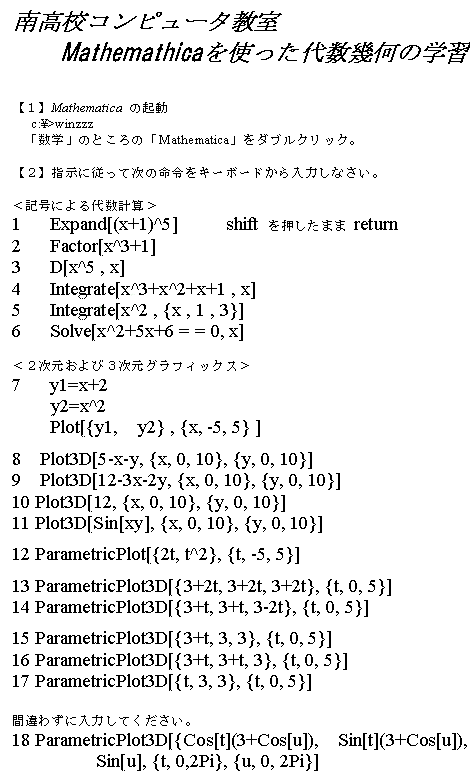
18個の命令群のプリント配布。それを注意深くひとつひとつ入力して結果を理解していきます。
最初は
Expand[(x+1)^5]
です。何だとお思いですか。(x+1)の5乗を展開してそのまま表示します。「かしこい」という声があがります。
次々にキーボードから入力します。
Factor[x^3+1]
--> 因数分解せよ
D[x^5,x]
--> 微分せよ
Integrate[x^3+x^2+x+1,x]
--> 積分せよ
これらを入力して、コンピュータが答えを数学表示するのを見て、「このプログラムはかなりかしこいぞ」と思ってくれます。
ただ、生徒たちの感想文にもでてきますが、「英語で入力しないとあかんかったから苦労した。ただ間違っていたら赤の文字で出たからけっこうわかりやすかった。」というように、キーボード入力には苦労していました。
3.平面・空間図形を表示する
この Mathematica は図形表示にも威力を発揮します。
y1=x+2
y2=x^2
Plot[{y1,y2},{x,-5,5}]
生徒たちは、「プロットしなさい、y1とy2を、xは−5から5まで」と理解できます。
いっぺんでうまくこのグラフがかけた生徒はとても喜んでいます。これくらいからかなり進度にばらつきがでます。Pとp、[と{ など注意深く入力できるかどうかです。
いよいよ空間図形に移ります。
Plot3D[5-x-y,{x,0,10},{y,0,10}] は次のように表示されます。
平面 z=5-x-y すなわち x+y+z=5 の表示なのです。
これで初めて生徒は、Mathematica を使おうとした意図を了解します。
「すごく楽しかった。入力するのは難しかったけど、図形がすごくきれいに出るのがよかった。図形を身近に感じることもできた。何度も使いたいです。」
と喜んでくれる生徒がでます。
まだ教えていないのですが、直線のパラメータ表示もだしておきました。
ParametricPlot3D[{3+t,t,t},{t,0,5}]
で、x=3+t,y=t,z=t (0<t<5) で表される直線表示ができます。
4.トーラスまで表示できた
授業をしたからには、なにか強いインパクトを与えたいものです。
Parametric3D [{Cos[t](3+Cos[u]), Sin[t](3+Cos[u]),Sin[u]},{t,0,2Pi},{u,0,2Pi}]
という命令を入力してもらうことにします。
最初に授業をした2年4組では岩下君だけが表示に成功しました。ディスプレイに色づけされたドーナツ状の3次元図が現れてきます。うれしいのでおもいきりほめます。周囲もすごいなあ、という表情です。
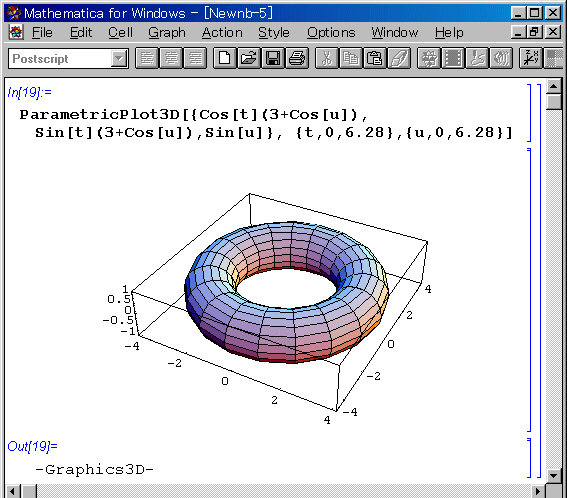
3次元トーラス図
時間終了です。
「残念だけどこれで終わります。最後の図形までいってほしかったけど、できたのは岩下君だけです。そのままスイッチを切らずにおいといてもらいますから、見に行ってください。それを見てから教室に戻ってください。自分ができてなくても、このプログラムを使うとこんな図形まで表示できることを見といてほしいのです。3学期授業が始まったらこのプログラムを道具として使ってみましょう。」
として授業を終わりました。
5.3学期の授業の中で
4クラスの生徒たちは、Mathematica を好きになってくれたようです。
直線と直線、直線と平面、平面と平面の問題など、生徒たちが問題を前にして、どう表示するかに苦労することで、空間図形の x,y,z の感覚が養えないか、パラメータ t をあやつることで、空間図形が思うように表示してしまうなどの生徒が出現しないか、3学期の授業を楽しみにしていました。
1995年1月17日の大震災は、学校生活にも大きな影響を与え、3学期中短縮授業が続きました。
Mathematica をもういちど生徒たちに使わせたい、と願いながらその時間が生み出せません。最後の週に理系クラス3年9組にその機会をつくることができました。
最後の章で空間内の平面の方程式、直線のパラメータ表示を学習しましたので「教科書の例題を3次元で確かめる」とした授業を行いました。
久しぶりのコンピュータ授業で生徒たちはうれしそうです。教科書を開かせ、最初の例題
「4x+3y+3z=16 はどんな平面か」
を表示せよとします。これはすぐ
z=-4x/3-y+16/3
と変形して
Plot3D[-4x/3-y+16/3,{x,0,10},{x,0,10}]
とすればよいことを伝えます。
生徒たちは今までノートと黒板に表示した平面や直線を、Mathematicaにキー入力命令することで、目の前のディスプレィに3次元表示させられることを喜んでくれました。
敬遠しがちな空間図形が身近なものに感じた生徒が多かったようで、次年度での再度の黒板授業が楽しみです。
|

