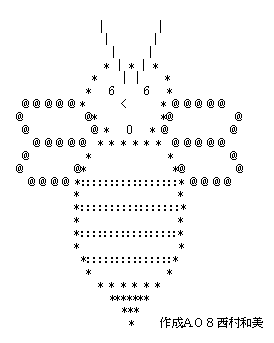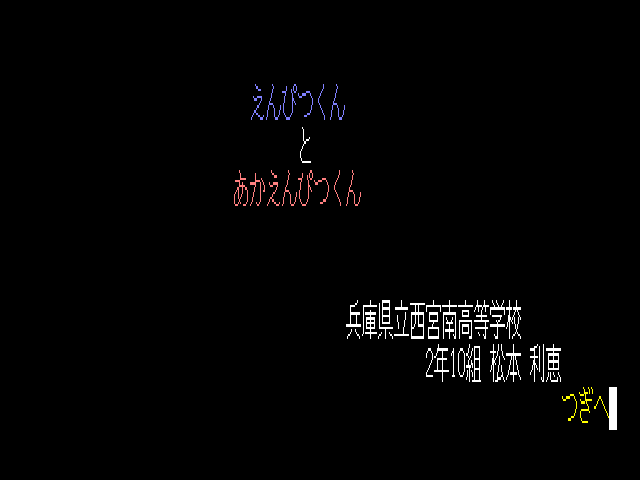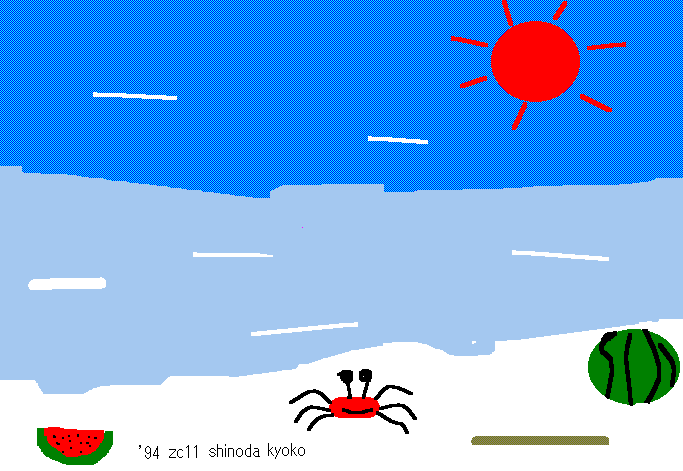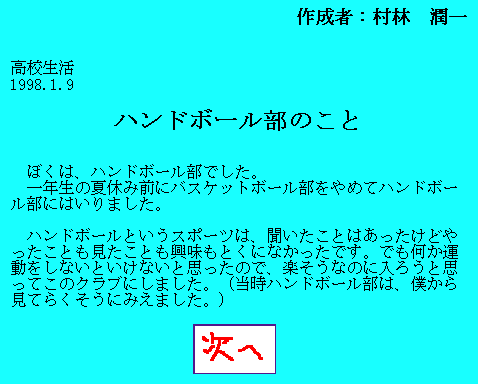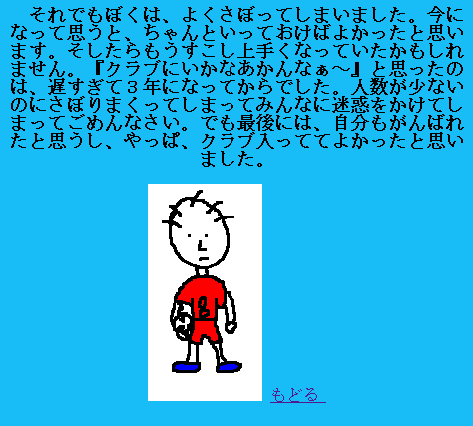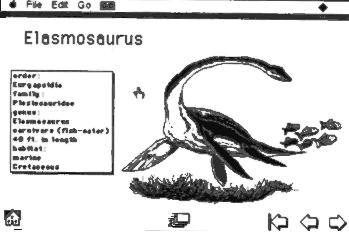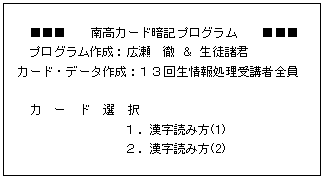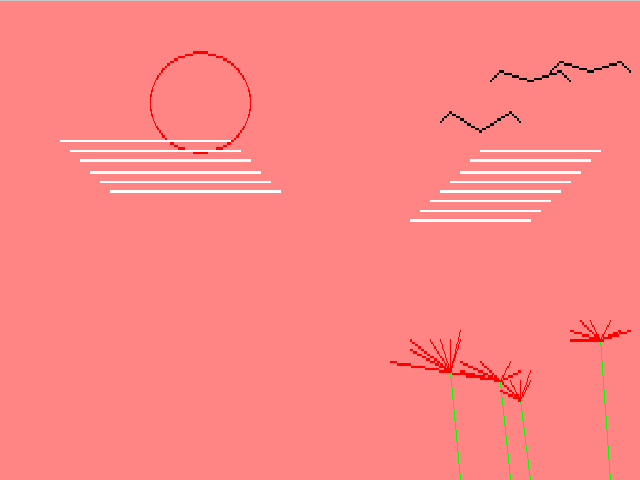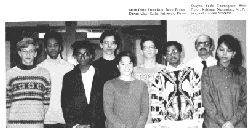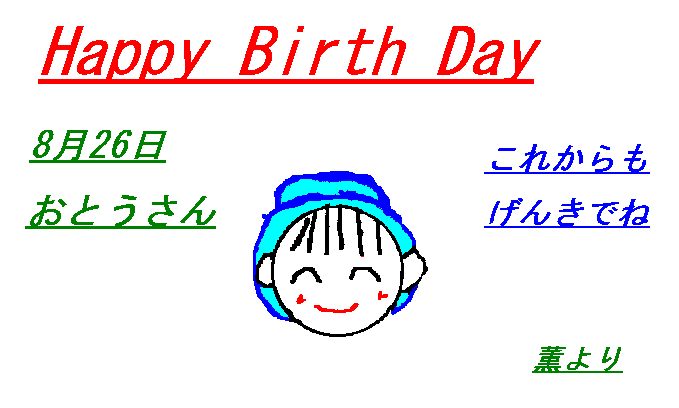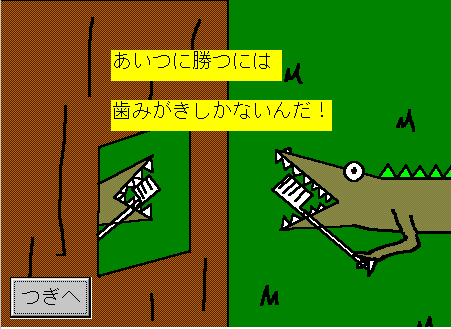1.単色であっても多彩な表現のできるマッキントッシュにであいました
1985年、「全国教育研究所連盟CAIプロジェクト」実験校として、本校に48台のIBM−JX5が設置されました。4、5年前まで続いていた選択科目「商業科情報処理」は、カタカナしか表示しないPC8001機10台という旧式機種のため、たち消えとなっていました。
ただこのJX5機もマイナーな機械であったため、時代はPC9801全盛期でしたからさわる教員も少なく、研究発表が終わり研究指定が終了すれば、昔のLL教室の運命になるのではという予感がありました。
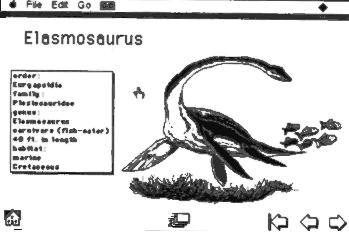
そのときわたしはアップル社のマッキントッシュというコンピュータに出会いました。今でも多くのファンを持つその機械は、モノクロ画面ながら、現在のウィンドウズのようなクリックによる画面展開、音や画像が表示しやすいハイパーカード方式(右図)という優れたシステムを実現していました。そしてそれを使って、生徒たち自身が作り上げる多彩な作品群が続々と生まれていました。本校に設置されたJX5は、現在のDOS/V機の原型であり、単色であれば似たようなことが出来る、JXも捨てたもんではない、絶対生徒の元気の出る授業が出来る、そう思えました。
1988年12月、進路の確定した3年生に希望を募って6日間の「冬休み臨時講座」を設けたのが私の最初の情報処理講座でした。5名の生徒と、ワープロ、マルチプラン、パスカルによる簡易プログラムをやってみました。力不足だと思っていたJX5は以外にいい力を持っていました。わくわくしながら1日ごとに授業を創っていったのを覚えています。
2.生徒は表現力を持っています
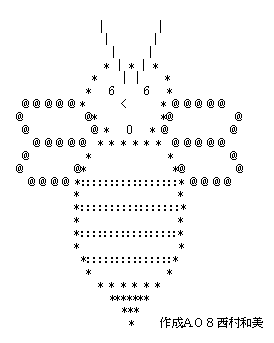
自作ソフトを使ったCAI授業は少数ではありましたが、数学・物理で意欲的に続けられました。1988年には、3年選択授業に「商業科情報処理」(2クラス各40人週2時間)が設けられ、ワープロとBASICの学習が始まりました。
1989年、初代の情報教育部長頼成氏の打診を受け、免許外申請の上「情報処理」(2クラス各35人週2時間)の授業を担当することになりました。
なにから始めるか迷いました。少なくとも、見本を見て全員同じものをまねさせるようなことだけはすまいと思っていました。時間もないことだし、少しだけ水に浮く方法を教えた後は、いきなりプールに放り込んで泳がすような授業方法を取ろうと決めていました。
キーボードの押し方を教えた後、私の最初の課題は「タイピング・グラフィックス」でした。キーボードのアルファベットや記号を使って、絵柄を画面に表示してみようというのです。最初に出会ったのがこの13回生西村和美さんの「みつばち」の図柄でした。
「生徒はこんなものを作る、ああ、わたしには出来ないものを持っている」ととても感動しました。いくつもの清新な図柄や工夫に感心しました。
生徒に自由に表現させたらきっといいものができあがる。今思えば、この確信が私の「授業への出発点」だったように思います。
3.生徒の力を合わすことでたくさんのものができました(1989〜 )
どうせコンピュータをさわるなら、どうせワープロをやるのなら、やったと意味のあるものをさせたい、そう思いました。
PC9801でつちかっていたBASIC言語のプログラムを、JX5機に試行錯誤しながら移植し、答え合わせプログラムを作りました。そしてこれに使える「問いと答え」のテキスト文を作ってもらうことにしました。
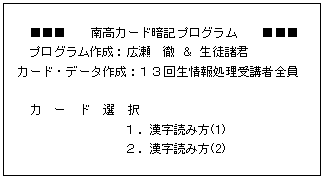
まず手がけたのは、生徒たちが9月に出会う就職試験の問題集を一人一人手分けして入力することでした。「基礎・受験英単語」「四字熟語」「県庁所在地」「文学史」など、実に54種類のQ&Aデータ集ができあがりました。
放課後、解放したコンピュータ室に希望者が集まってこの「南高暗記カードプログラム」を学習していました。自分でなくとも同期生の作ったデータを利用するのです。気合いがはいっていました。
そのほかに、JX5は演奏もできましたから、小学校音楽の教科書からのメロディ入力集、古典教科書よりの枕草子古文及び現代語訳の77段の入力、百人一首カルタ作り、点字印刷のための本一冊のテキスト入力、数学CAIのための教科書入力、市役所発行の西宮市百景案内文入力、文化祭の脚本入力、・・などさまざまな入力を行いました。
できあがると、とてもひとりでは出来ない大部のものができあがる。これは生徒にとっても教師にとっても大切な体験でした。
4.BASIC言語で「春夏秋冬グラフィックス」を表現(1990〜94)
JX5の基本モードBASICは、80文字×10行という変形縦長文字でしたが、16色の表現力のあるモードを持っていました。自分の思い通りの表現をカラフルにさせたい、そう思って、線や長方形のline文、点を打つpset文、色を塗りつぶすpaint文、円や楕円を描くcircle文、だけを教えたあと、「春夏秋冬のうち自由な季節を選んで表現しなさい。」と課題を出しました。
当時、岡田俊一氏指導で須磨友が丘高校の生徒たちがコンピュータグラッフィクスを作っていました。そのいくつかをJX5に移植して、授業中に見せました。同世代の作成です。遠くに思えていたコンピュータプログラムがわたしたちにも出来ると思ってくれたのでしょうか、猛然と作り始めました。
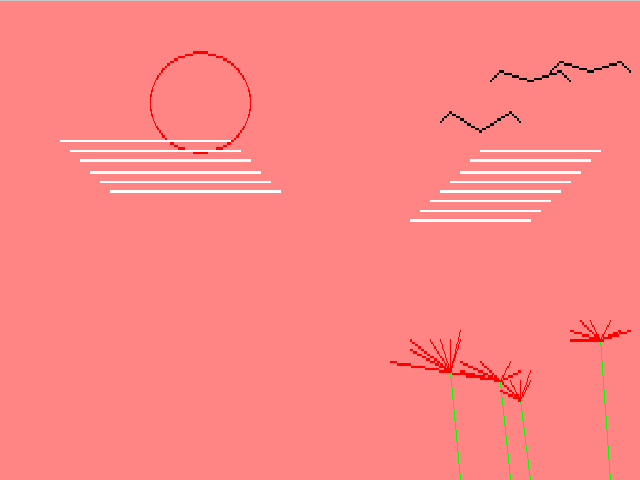
図柄を方眼紙上に描き、その点の座標を取り、line(x1,y1)-(x2,y2)で結んでいく、といったていねいなプログラムを作り上げました。
最初の年1990年にできあがった作品群は清新なものでした。プログラムが走り始めると、生徒が打ち込んだ1行1行の命令に即したカラフルな表示がひとつひとつ画面に表示されていく、それは大切な感動の一瞬一瞬でした。<作品は、17回生福田亜紀さんの「秋」>
その中で生徒たちは、だれもがすぐ考えつく「白色と円だけの雪だるま」「青い海と太陽」では、自分を表現できないと気付くものが出てきました。なるほど、と思える作品は生徒たちに採点投票させても高い評価が出ます。他の生徒が実現しているのを見ることで、「自己表現すること」は恥ずかしいことでもためらうことでもないのだと分かっていく生徒が少しづつ増えていきました。
5.そうだ「おとうとやいもうとたちへ」プログラムだ!(1990〜 )
わたしたちのコンピュータ教室は西端にあるC棟にあり、となりには高須西小学校の校庭があります。廊下で生徒たちと話していると、校庭いっぱいに遊ぶこどもたちの声が聞こえてきます。
そうだ、あの子たちをこの部屋に呼んだら、どんなに喜ぶだろう、その小学生たちに見せるプログラムを作ってもらうのなら、生徒たちはきっと喜んで作ってくれる。そうだ、「おとうとやいもうとたちへ」のプログラムだ。そう思いつきました。
半年しか学んでもいない生徒たちに、そんなプログラムの授業はどんな意味があるのか。
ねらいをBASIC言語の習得に置くのではなく、「構想を立てる力を養う」「一歩一歩組み立てていく過程(段取り)の大切さを伝える」「いろいろな自己表現があることをお互いの作品から学ぶ」ことにおきました。
ラベルすら使えない原初的なJX−BASICでしたが工夫次第です。設計を十全にさせ、コーディング用紙に書き入れてからしか入力させないことを固守しました。スタートから GOSUB 1000, GOSUB 2000, GOSUB 3000 というように、プログラムを構造化する作法を徹底して伝えました。
色を混ぜる、画像を表示するなどのプログラム的に難しい部分は、発注されたものとして私がサブルーチンを用意して、それを関数としてポンと利用するという手法を使いました。
ゲーム風にするためのさいころをふるサブルーチンや、平安時代の画面のための縦書きサブルーチン、スキャナー画像を表示するサブルーチンなど次々に作りました。身近にはそうしたぼうだいな時間を費やす苦労をともにする同志は少なかったので、当時伸長してきたパソコン通信の、全国ネットPC−VAN「教育とソフト(STS)」の仲間に随分教えていただきました。PC9801の単色スキャナー画像をJX5で表示できるなど、自分だけではできることではありませんでした。
そうやってできた最初のプログラム群は予想をはるかに越えた作品群でした。紙芝居風おはなしプログラム、童謡のイントロクイズ、スロットマシーン、画面いっぱいのアニメキャラクター・・・・。
いくつかのプログラムは全国の通信仲間に見てもらいたくて、PC9801へ移植しました。その一つの一画面をお見せします。
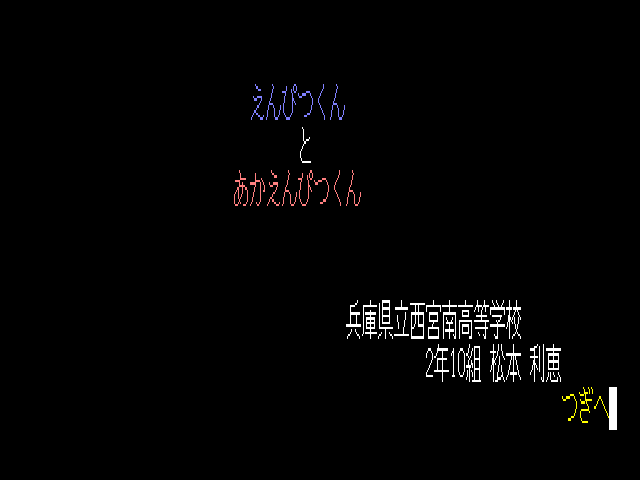
15回生松本利恵さんの「えんぴつくんとあかえんぴつくん」です。ちびてきて、すてられそうになったえんぴつくんたちがどうしたのか、画面がぱっとかわるとこのシーンが少しづつ表示されていきます。次の年の「夏休みこどもコンピュータ教室」に来てくれた30名の小学生は、高校のおにいちゃんやおねえちゃんが作ったのだと説明するとうれしそうに見てくれました。もうその小学生たちが本校に入学・卒業しています。
6.ピーボディ高校と英文メールの交換、世界が見えた(1990 〜 91)
1990年、情報処理の授業が、長文読解・英文法・古典などと同枠の選択教科として2年生から設置することとなりました。授業者としては2年間学習すればどこまで伸びるだろうかという期待がありましたし、当時の中学からの生徒の荒れをどうやって汲み取っていくかという教科の工夫としても職員会議のカリキュラム討議の上決定されました。
最初の2年間の弟子たちに何を伝えるのか、プログラム技術の強化ではありません。コンピュータのもういひとつの面、電子による情報伝達だろうと思い当たります。
幸い私はコンピューサーブという世界パソコン通信に加入していましたので、その電子メールが使えました。PC−VANのSTSにそうした国際通信のグループ結成が行われ、海外との交流が熱心に議論されました。
アメリカ合衆国ペンシルヴァニア州ピッツバーグ市のピーボディ高校との英文電子メールのやりとりを、情報処理受講の2年生が始めることにしました。簡単な自己紹介から始まって、日本の習慣や文化を英文化する作業を、ALT講師のリサ・イソベ先生にも添削いただきながら、授業の中で始めました。相手校の担当教師は社会科のレン先生で、「ステレオタイプ(型にはまった)なものの見方をさせたくない。」とその動機を伝えてくれました。
全員一人一人に署名入りの返事が来ました。どんな人だろうとそれぞれとても興味深げでした。このときはっきりしたことがあります。それはユニークな文章を書いたものにはそれなりの内容を書く人が返事をくれたことでした。リサ先生がいつも言われていたことですが、「京都は美しい街です。」と書いてもなにも伝わらない、どこがどう美しいのかを書かなければならない、ということが実感として分かります。
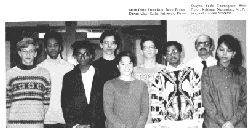
そしてその夏、ピーボディ高校から日本へサチさんを迎えました。プレゼントとして持ってきてくれたのが、全校生の個人写真も載っている学校アルバムでした。文通の相手の顔がひとりひとり分かります。リサ先生の言われていた「外人とまとめて言って欲しくない。アメリカ人、フランス人、もっと言えば、ジョンであるし、ポールです。一人一人を見て欲しい」ことが少し分かっていきました。
そのことは湾岸戦争の手紙のやりとりでもっとはっきりしました。「戦地から若者が無事で帰ってくるよう、どの家のドアにも黄色いリボンが付けてあります。」と書かれるレン先生にはとおりいっぺんの戦争反対だけを書くことが出来ません。わたしたちの戦争への反省から書いていくことになりました。
ピーボディ高校のコンピュータの故障と、お互いの生徒たちの卒業で、2年間だけの交流に終わりましたが、英文字をディスクに書き込むコンピュータが、世界を見せてくれる手伝いをしたのでした。
7.マルチメディア機導入、小学生が最初の使用者(1994夏〜 )
県下普通高校で最初の1人1台のコンピュータ環境も導入時(1885年)から9年を過ぎていました。コンピュータを通じていろいろ伝えたいこと、ともに作りたいことはいっぱいあって困ることはなかったのですが、学校の中にJX5をさわろうとする仲間が増えないのだけは難儀しました。しかしついに環境整備も県下を一巡し、普通高校としてウィンドウズ機を導入するという先頭を切る役目が回ってきました。
1994年8月、当時の最新機種ウィンドウズ3.1の走るIBM−PS/Vが40台設置されました。256色のカラー表示、音声・音楽、CD−ROM写真画像の表示など、マルティメディア環境としてがらりと一新した機械設置でした。
8月末に開くことになった「夏休みこどもコンピュータ教室」の小学生が真っ先の使用者となりました。花をクリックすると花が開く、牛を押すとモーと鳴く、などしかけを満載したCD−ROMソフトに、集まったこどもたちは歓声を上げていました。
1日目ウィンドウズ入門、ペイントブラシでのグラフィックの描き方を教えた後、「お母さん、お父さん、身近な人へ、自分の気持ちを伝えるカードを作りましょう。明日作りますから、図柄など下書きをしてきて下さい。」と宿題を出しました。
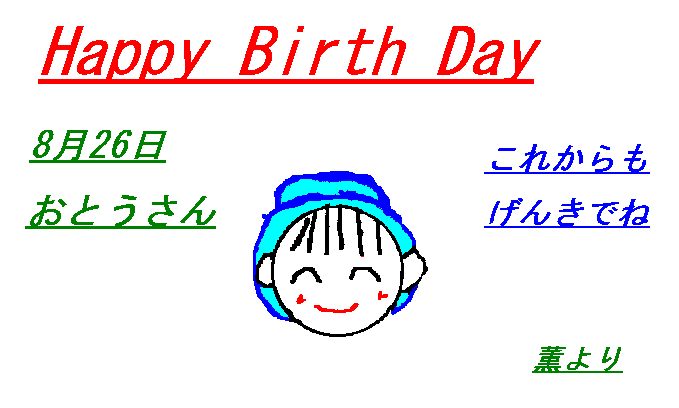
次の日、1時間ぐらいでできあがった一つが、6年生、薫さんの誕生日おめでとうカードでした。本当に明日がお父さんの誕生日でした。購入したばかりのカラープリンターで印刷して持って帰ってもらいました。
初めてさわる小学生が、たった2日でこれだけのものを作ることができる。おとうさんの誕生日に渡して喜んでもらいたいという薫さんの思いが、宿題のデザインをしっかり下書きして、気合いを入れてマウスで描画したのです。
保護者の許可もいただいて、この絵をいつも生徒たちに見せまて伝えます。「自己を表現するということは、表現したい自分が強くあるときに実現できることなのです。明日はお父さんの誕生日、お父さんの喜ぶ顔が見たい、この気持ちがこの絵を描かせるのです。」
そういった気持ちを1日で表現できるウィンドウズのマルチメディア環境は、生徒たちにも大きな道具になれそうでした。
8.生徒の作るポスター・コンピュータグラフィックス(1994秋〜 )
1994年夏に設置されたウィンドウズ機を使って最初の授業が始まりました。
折しも西宮南高校は20周年を迎えようとしていました。よし、20周年記念ポスターを作ってピロティに展示し、生徒たちを表舞台に出そう。コピーフリーの3000枚の写真集CD−ROMを1台1枚購入してありましたから、それにカラフルな文字を付けるだけで見栄えのするポスターができるはずだ。
そのとおりでした。張り出された「創立20周年記念ポスター」は同級生からも担任団からも「すごいなあ」とほめてもらいました。だんだん生徒たちも照らいがなくなりはじめました。

JX5−BASICで作っていた「春夏秋冬グラッフィクス」をウィンドウズで作ってみることにしました。
下の絵は、19回生篠田香子さんの「夏」のグラフィックですが、スイカとカニの色合いがとてもよく出ている作品でした。
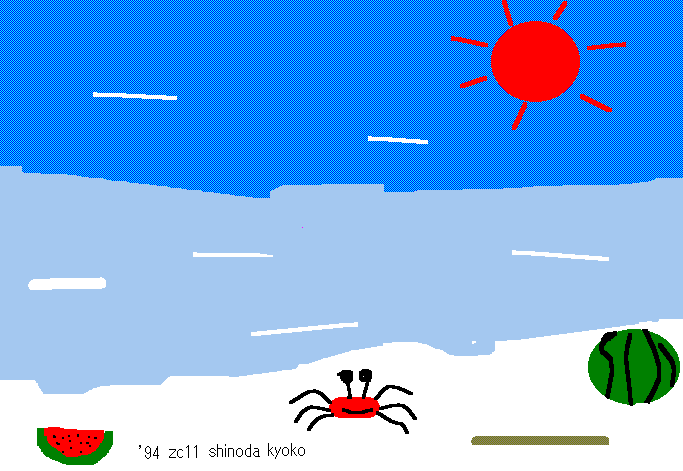
以後、毎年埋もれさすには惜しい作品が続々と出来ています。
9.高校生がウィンドウズプログラムを作る(1995〜 )
ウィンドウズの導入期、授業としてのプログラム学習をどのようにするか、情報教育委員会で何回も議論しました。そしてやはりやってみよう、ということになりました。
当時、格段に複雑になったウィンドウズシステムでプログラムが組めるのはプロのプログラマーでもまれでした。ちょうどその頃その要請なのでしょうか、VisualBasicという日曜大工的プログラム言語が発売されました。使ってみて、画像表示、画面ジャンプ、ぱたぱたアニメ、音声ぐらいの限られた手法なら、生徒たちにもやれると見通しがつき、40本購入しました。
次の年、1995年秋、2年から継続して受講している生徒たちに「全国でも高校生として初めてのウィンドウズプログラムを作りませんか。夏休みにくる小学生を喜ばせようよ」と提案しました。半信半疑ながら始めてくれました。
まず設計図です。画面の切り替えによる「紙芝居風プログラム」、色々な場所をクリックするとなにかが起こる「遊園地型プログラム」、答え方によって枝分かれしていく「分岐型プログラム」の3つを提示しました。
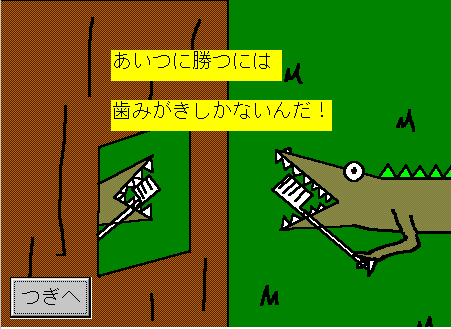
たくさんの名作が出来ました。19回生関戸貴子さんの”虫歯とたたかう「ワニ男くん」”の8画面目をあげてありますが、作品紹介の窓にこう書いてあります。
「私は最初、小学生にみせる、と聞いたので動物がでてくる物語を、作ろうと思いました。何となく、歯みがきの事を、アピ−ルしたくて、ワニに決めたのは、いいんだけど、なかなかワニくんが書けなくて苦労しました。物語を考えていくうちに、次々といろんなシ−ンが、頭に浮かんできて、すっごく楽しかった。
でも、問題はこれから。。。。。紙の上に書くのと、コンピュ−タ−の画面に書くのとでは、ぜんぜん、違う。かわいらしく書いたつもりが、まるで、おどかしてるようになっちゃって、わ−−−−!と、何度も叫びたかった。それも、乗り越えて、コツをつかめばこっちのもの、すらすらと、できあがります。ますます情報処理が好きになりました。たのしんでもらえたなら、うれしいです。つかれました。」
生徒が持っているやさしさをこんなふうに引き出せるのなら、手間ひまをかけた準備もまたうれしいこととしてあります。
10.みんなで工夫していろいろな教材を作りました(1995〜 )
1995年になって情報処理を担当する教師が相互乗り入れをして、自発的に2人担当としました。次の年、職員会議に図り制度的な了承を得ました。そのおかげで、現在までに7名の授業経験者が生まれました。
毎年さまざまな取り組みが工夫されました。表計算ソフト「ロータス123」を使って、日本全国の都道府県別データ集を解析してそれから情報を抽出する授業、野球選手の実際の打率データの解析、2週間4回の授業で大相撲の勝敗を書き入れながらのデータ解析。ワープロソフト「一太郎」を使って、家庭や趣味・クラブ活動を取り上げた壁新聞の作成、歌集や文集の作成、ひとりひとりに問うアンケートを実施してこれをレポートとしてグラフなどを使ってプレゼンテーションとして提出する授業などそれぞれ工夫した教材を考えました。
尼崎産業高校を見学させていただいたとき、ディズニーランドへ行ったつもりの旅行報告書作成の授業に出会いました。アイデアをお借りすることをお願いして、帰りに2、3の旅行社へ寄り100枚ほどのひとつひとつ違った旅行パンフレットをもらってきました。
しかしどうもなにか足りない、インパクトに欠ける気がします。1週間ほど考えていて、ふっと「おとうさんやおかあさんのための旅行プラン」と思いました。そうだ、それなら作ろうと思ってくれるんではないか。
授業の冒頭こう話します。「プレゼンテーションとしてのワープロ文書作成のテーマとして、おとうさんやおかあさんのための旅行プランを作りませんか。おとうさんやおかあさんのおられないうちもあると思うけど、逆に2倍苦労をかけているのだから、2倍いいプランをたてませんか。」 ためらわれますが、そのことで引き起こすことは引き受けるつもりであれば言うしかありません。きっと生徒は率直に受け止めてくれるはずです。
「おかあさん、北海道へ行きたい、言うとった。」「ヨーロッパに夫婦で行かせよう。」
など、パンフレットのまわりでさかんに話しています。楽しそうに作り始めます。写真を一つだけ入れていいから、ここでスキャナーに読み込んで画像ファイルにしたげるよ。」と言いますと、エッフェル塔、紅葉の風景、おいしそうな旅館の料理、・・などひとりひとり選ぶ写真が違います。
1台だけあるカラープリンターを使うことにします。カラーインク代は必要経費です。「おかんのための旅行プラン」と大きく題書したものもできあがりました。
「たった1枚だけのカラーパンフレットです。きょう親に渡して下さい。もし黙って受け取るだけであっても、絶対親は喜んでいることは信じてやって下さい。」と言っておきます。
あとで感想を書いてもらう機会がありました。じつにいろんなドラマが起こったようです。
自分を表現してそれを相手に伝える、これが情報発信です。1年間、2年間そのことを伝えていけば、ずいぶん生徒たちは変化しました。
ただそうもいかない個性があることも事実です。前述の「おとうとやいもうとたちへのプログラム」を作ろうと提起したとき、5時間腕をこまねいて画面を見つめる生徒が3年生に2人出ました。画面図になにか書き始めてごらんよ、というのですが、始めません。なんでもいいんですよ、といわれると、言われれば言われるだけ、どんどんどうしていいか分からなくなるようです。たぶん少し話をしてこんな物語をつくってごらんよ、と中身を言ってやれば作り始めるでしょう。しかしそれだけはすまいと思っていました。自分で踏み出すしかない。踏み出せないものほど、助けに行ってはいけないのです。自分でそのことを乗り越えた経験がない限り、以後その乗り越え方が身に付きません。ほかの生徒はどんどん作り始めている中、そのふたりはずっと腕組みでした。
5回目をすぎてようやく、ひとりが口をひらきました。「俺、みんなみたいに絵うまくないし・・」 「なに言うてんの、字だけだって小学生のよろこぶもの作れるで、色もつけられるし。」ようやく始めました。できはよくありませんが、とりあえずは自分の考えで文字だけのものを二人とも作成しました。
自分で考えろと言い続けて、5時間をじっと待つこと、これがふたりへの授業だったように思います。自由にしていいと言われたら、途方にくれるこどもたちを、わたしたちは大量につくっているのではないか、情報処理の授業をしていてとてもそう思います。
11.わたしたちからの情報発信−HTML文書の作成(1996〜 )
1996年秋、本校にもホームページによる情報発信を始めようと職員へ提案しました。1年ほど前から、ハードディスクの中に、アカデミーフリーの英語版ネットスケープが動くようにして、パリのルーブル美術館ホームページ、沖縄県美里高校のホームページ、徳山天文台ホームページなどをディスクから見せていました。
そのもとになる文書は、たとえば <H1>修学旅行の感想</H1> と書くだけで1番大きい文字で 修学旅行の感想 と画面に表示されます。こういうのをHTML文書というのですが、簡単なものなら案外たやすく作れます。もちろんカラー画像が貼り付けられます。いわば、ホームページとはカラーパンフレット集だと思ってもらったらいいでしょう。その原版は生徒たちに十分作れます。
学校としてホームページを開設し、学校新聞を始め多くの学校情報を発信する、そして生徒たちがそれを作る力を持つなら、高校現場からの生き生きとした情報を、保護者・地域・卒業生、そして全国、さらに世界へ発信することも可能です。
経費についての事務の了解、職員会議の了解、管理職の了解のもと、1997年4月、「西宮南高校ホームページ」が開設されました。
そして、授業の中で本格的なHTML文書の作成に入りました。開かれていることの責任、プライバシー保護を考えた上で、外の世界に発信する内容を持つのか、なかなか厳しいことがらです。
下は、21回生の村林潤一君の作成したページ「ハンドボール部のこと」です。さし絵の何ともかわいらしいページです。
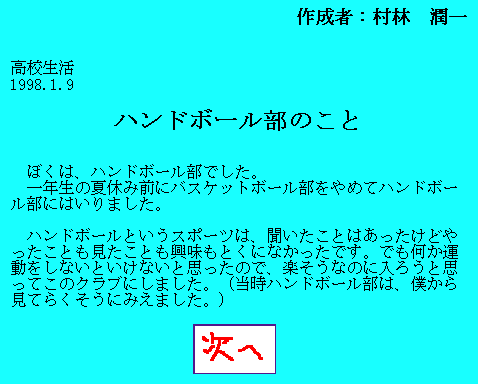
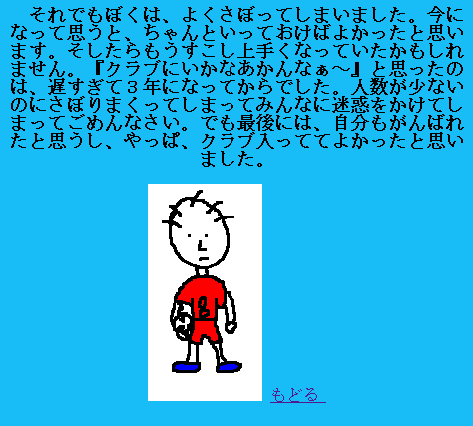
もし個人のホームページとしてなら、自分の責任においてもっと広い情報発信があるでしょう。表現する自己を持っているのかどうか、いよいよ問われる時代に入っています。
HTML文書は簡単に音声も出せますし、プレゼンテーションとしてのプログラム言語でもあり、どんな機種にでも表示できる広範な拡張性を持っています。
情報処理授業を始めて10年、ついにそういった時代にはいりました。
12.生徒たちに、精一杯の表現をさせたい
情報処理の授業は、確かに手間ひまはかかります。
思いついたことを授業にまで持っていくには、たとえば100枚のパンフレットを集めること、ひとりひとり設計図を点検助言すること、ひとりひとり違った写真をスキャナー画像に保存してあげること、そしてできあがった作品をみんなが見ることが出来るよう展示したりディスク収納すること、10年後に見ませんかと卒業時タイムカプセルとしてディスクを手渡すこと、どれをとっても手間ひまのかかることです。
しかし、授業といっしょです。生徒のよろこぶ顔がみたい、そのためならその手間ひまは惜しくない、そう心決めればいいことです。
自己を表現させることは、ほっといて自由にさせることとはまったく違って、できたものがいいものならそのほうがいい、今度は自分だけで作っていく、そうして生徒は高みにのぼるうれしさを会得するのだと確信できます。
そういう意味で授業もまた「ひと」がつくるわけで、そのひとの個性でしか授業は作れないことは十分わかってはいても、それでもこんな授業しませんかとお誘いしたくて、10年を契機にまとめてみました。
やはりコンピュータは、人間が基本です。
1998.3.19
|